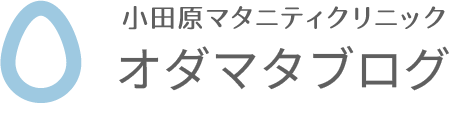近年、晩婚化が進み、不妊治療を受けるカップルが増えています。その中でも体外受精(IVF)は、妊娠を望む多くの人々にとって重要な選択肢となっています。一方で、「体外受精で生まれた子どもはダウン症のリスクが高いのか?」という疑問を持つ人もいるでしょう。
今回は小田原マタニティクリニックより、体外受精の場合はダウン症が高いのか低いのか?という点をテーマにお届けしていきますので、ぜひご覧ください。
ダウン症について
ダウン症(21トリソミー)は、通常2本あるはずの21番染色体が3本あることで発生する先天性疾患で、知的発達の遅れや身体的発達の遅れなどがあります。
ダウン症の発生率は母親の年齢に大きく影響され、一般的に、20代では約1,500人に1人、35歳では約350人に1人、40歳では約100人に1人の割合で発生するとされています。
体外受精とダウン症の関係
続いて、体外受精とダウン症の関係について見ていきましょう。
自然妊娠と比較して発生率は少ないのか?
基本的に体外受精自体がダウン症のリスクを低下させるということはないとされています。体外受精であっても、母親の年齢が高い場合には自然妊娠と同様にダウン症のリスクが上昇します。ただし、体外受精には特定の技術が用いられることがあり、それが結果的にダウン症の出生率に影響を与える可能性があります。
着床前診断(PGT-A)の影響
体外受精では、受精卵を子宮に戻す前に「着床前診断(PGT-A)」を行うことが可能です。PGT-Aは、胚の染色体異常を検査し、正常な染色体を持つ胚のみを移植する方法です。これにより、ダウン症などの染色体異常を持つ胚が選別されます。
ただし、PGT-Aの実施には制限があり、すべてのカップルがこの検査を受けられるわけではありません。
顕微授精(ICSI)の影響
顕微授精(ICSI)は、精子を直接卵子に注入する技術であり、重度の男性不妊のカップルに多く用いられます。この方法がダウン症の発生率に影響を与えるかどうかについては研究が進められています。
体外受精を考える際のポイント
続いて、体外受精を考える際のポイントについて見ていきましょう。
年齢と卵子の質
体外受精では、基本的に母親の卵子が使われるため、年齢が高くなると染色体異常のリスクも上がります。そのため、体外受精で妊娠を目指す場合でも、なるべく早い段階で治療を開始することが重要です。
出生前診断の活用
体外受精に限らず、妊娠後の出生前診断(NIPTや羊水検査)を受けることで、胎児の染色体異常の有無を知ることができます。PGT-Aを実施できる場合、胚の染色体を確認したうえで移植が行われるため、妊娠率の向上や流産率の低下が望めます。特に高齢妊娠の場合は、検討する価値はあるでしょう。
まとめ:体外受精の場合ダウン症は少ない?体外受精とダウン症の関係について
いかがでしたか?今回の内容としては、
- ダウン症は21番染色体の異常によって発生し、母親の年齢が高いほどリスクが上がる
- 体外受精自体がダウン症のリスクを下げるという根拠はない
- 体外受精での「着床前診断(PGT-A)」により、染色体異常を持つ胚を除外することは可能
- 顕微授精(ICSI)自体がダウン症のリスクに影響を与える明確な証拠はない
- 体外受精を考える場合は、年齢や卵子の質を考慮し、医師と十分に相談することが重要
- 出生前診断(NIPTや羊水検査)を活用することで、胎児の染色体異常の有無を確認できる
以上の点が重要なポイントでした。体外受精は妊娠の可能性を高める技術ですが、体外受精の場合はダウン症は少ない、ということはありません。正しい知識を持ち、医師と相談しながら適切な判断をすることが大切です。