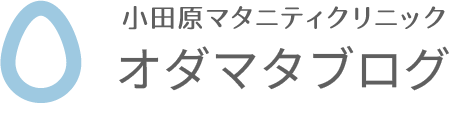かつては高額な自費診療が前提だった不妊治療ですが、2022年4月より不妊治療の一部に公的医療保険が適用されるようになり、大きな変化がもたらされました。これにより、多くの夫婦が経済的負担を軽減しながら治療を受けられるようになっています。
しかし、不妊治療に保険が適用される範囲や条件について、まだ正確に理解していない方も少なくありません。今回は小田原マタニティクリニックより、「不妊治療の保険」に焦点を当て、制度の概要から利用方法、対象となる治療内容まで詳しく解説します。
不妊治療に保険が適用される背景
不妊は誰にでも起こり得る現代的な課題であり、日本では6組に1組の夫婦が不妊に悩んでいるといわれています。そのため、政府は少子化対策の一環として、不妊治療への保険適用を進めてきました。
2022年4月の制度改正により、タイミング法、人工授精(AIH)、体外受精(IVF)、顕微授精(ICSI)といった生殖補助医療の一部に保険が適用されるようになり、経済的な負担が大幅に軽減されています。
不妊治療で保険が適用される範囲
続いて、不妊治療で保険が適用される範囲について見ていきましょう。
対象となる治療
現在、保険適用となる不妊治療には、以下のような内容が含まれています。
まず、タイミング法や排卵誘発剤を用いた治療が適用範囲に入ります。これに加え、人工授精(AIH)や、体外受精・顕微授精といった高度生殖医療も一定条件のもとで保険が使えるようになっています。
ただし、体外受精や顕微授精については、1人の子どもを出産するまでに保険適用できる回数が年齢によって制限されています。たとえば、治療開始時に40歳未満の場合は最大6回まで、40歳以上43歳未満の場合は最大3回までが保険の対象となります。
年齢や回数による制限
保険の適用には年齢や回数の制限が設けられており、誰でも無制限に使えるわけではありません。これは医学的根拠に基づいて決定されており、高齢での治療成功率が下がることや、社会保険制度の持続可能性を考慮したものです。
また、夫婦ともに一定の条件(婚姻関係、事実婚など)を満たしている必要があります。治療を受ける医療機関が厚生労働省の指定を受けていることも、保険適用の前提条件となっています。
自由診療との違い
保険適用の不妊治療と自由診療の不妊治療では、治療内容や金額、使用する薬剤、技術の幅に違いがあります。保険適用の治療では、国が定めた範囲内の標準的な治療が行われるため、治療の自由度はやや制限されます。
一方、自由診療では医師と相談しながら個々の状態に応じた柔軟な治療計画が立てられるというメリットがあります。ただし、その分費用は全額自己負担となります。たとえば、着床前診断(PGT)や特殊な培養液を使用した受精卵の育成といった高度な技術は、自由診療となります。
「混合診療」は原則として認められていない
初診時には問診やホルモン検査、超音波検査などが行われ、どの段階の治療から始めるべきかが医師と相談されます。また、治療が保険適用の範囲内かどうかは医師の判断により決定されます。保険診療と自由診療を同時に併用する「混合診療」は原則として認められていないため、保険診療と自由診療は別々に行う必要があります。この点は治療計画を立てる上でとても重要です。
今後の制度の動向と課題
不妊治療の保険制度は導入から日が浅く、今後も対象治療の範囲拡大や制度の柔軟化が期待されています。しかし、現時点ではカバーされていない治療も多い点に注意が必要です。また、制度の認知不足や、保険対象であっても現場での運用にバラつきがあることも指摘されています。患者としても、最新の制度情報をしっかり確認しながら、自身にとって最適な治療を選択することが求められます。
民間の医療保険について
民間保険のメリットは、公的保険でカバーされない部分まで保障していることがあるため、治療の幅広い選択肢をサポートします。しかし、民間保険は月々の保険料が発生するため、そのコストを事前に把握し、自身の経済状況に応じて選択することが重要です。治療を受ける前に、十分な情報を収集し、最適な保険プランを選ぶことが大切です。
まとめ:不妊治療に保険は使える?制度の仕組みと利用のポイントを徹底解説
いかがでしたか?今回の内容としては、
- 2022年4月から不妊治療の一部に保険が適用されるようになった
- タイミング法、人工授精、体外受精、顕微授精などが対象
- 年齢や治療回数に制限がある(40歳未満で6回、40歳以上43歳未満で3回)
- 保険適用の治療と自由診療には内容と費用の違いがある
- 混合診療は原則禁止のため、治療の進め方には注意が必要
以上の点が重要なポイントでした。保険制度の活用は、妊娠を望む多くのご夫婦の支えになります。制度を正しく理解し、賢く利用しましょう。