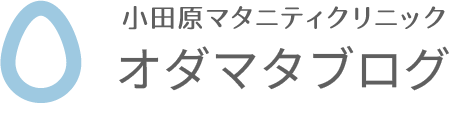不妊治療に取り組んでいる方の中には、「BT」という言葉を耳にしたことがある方も多いでしょう。BTとは「Blastocyst Transfer(胚盤胞移植)」の略称で、体外受精(IVF)や顕微授精(ICSI)において、受精卵を胚盤胞の状態まで育ててから子宮に戻す方法です。
受精卵が胚盤胞まで成長する確率は決して高くありませんが、その分、より着床能力が高い胚を移植できるのが特徴です。不妊治療の中でも、妊娠率向上を目指した重要な選択肢の一つとして注目されています。
今回は小田原マタニティクリニックより、BT(胚盤胞移植)をテーマにお届けしていきますので、ぜひご覧ください。
胚盤胞とは?BTとの関係を解説
胚盤胞とは、受精卵が細胞分裂を繰り返し、およそ5~6日目に到達する発育段階です。受精卵は、分割期胚(2分割、4分割など)を経て、やがて球状の構造になります。これが胚盤胞であり、着床直前の状態です。
BTはこの胚盤胞の状態で子宮内に戻すことによって、自然妊娠に近いタイミングと環境で着床させることができます。分割期胚に比べて、より発育の進んだ胚を選別して移植するため、妊娠率が高まるというメリットがあります。
BT(胚盤胞移植)のメリットとデメリット
BTには多くのメリットがありますが、リスクや注意点も存在します。まずメリットとして挙げられるのは、着床率の高さです。胚盤胞まで成長した胚は、着床する力が強く、自然妊娠と同様のタイミングで移植されることで、子宮内膜との同期も取りやすくなります。
また、胚盤胞まで育つことで、より良質な胚を選ぶことが可能になり、多胎妊娠のリスクを抑える目的で単一胚移植(SET)が推奨されることもあります。
一方で、デメリットとしては胚盤胞まで育つ胚が少ないため、全ての受精卵が移植までたどり着けるわけではありません。特に40代以降の女性では、胚の発育停止が多くなる、つまりは
移植できなくなる傾向があります。
BT(胚盤胞移植)は誰に向いている?
BTは年齢や卵巣予備能、これまでの治療歴などを総合的に判断して、医師と相談の上で決めることが重要です。例えば、30代で比較的採卵数が多く、良好胚が複数得られる可能性が高い場合には、BTが有効とされています。
BT(胚盤胞移植)当日の流れと注意点
BTは、外来での短時間の処置で終わることが一般的です。移植の直前には超音波で子宮の状態を確認し、カテーテルという細い管を用いて胚盤胞を子宮内に移植します。処置自体は5〜10分ほどで完了しますが、その後はしばらく安静にして過ごすことが推奨されます。過度な運動やストレスは避け、体を冷やさないように心がけましょう。
また、BT後に使用されるホルモン補充(黄体ホルモン投与)も着床維持のために重要です処方された薬剤は指示通りに継続することが求められます。
BT(胚盤胞移植)後の判定と心構え
BTから約10〜12日後には妊娠判定を行います。血液検査でhCGホルモン(ヒト絨毛性ゴナドトロピン)の数値を確認することで、着床しているかどうかを判断します。
妊娠判定日までは不安な気持ちが募る時期ですが、できるだけ穏やかな気持ちで過ごすことが大切です。自己判断で薬を中止したり、異常があっても我慢せずに医療機関へ相談する姿勢が求められます。
まとめ:BTとは?不妊治療における「胚盤胞移植」の重要性
- BTとは「胚盤胞移植」のことで、自然妊娠に近いタイミングで胚を戻す方法
- 胚盤胞まで成長した胚は、着床率が高く、より良質な胚を選別できる
- すべての胚が胚盤胞まで育つわけではない
- BTは外来で短時間に行われる
- 妊娠判定までは穏やかに過ごすこと
以上の点が重要なポイントでした。BTは不妊治療における有力な選択肢の一つですが、その効果を最大限に引き出すには、適切な判断と医師との密な連携が不可欠です。自身の体と心と向き合いながら、一歩ずつ前進していきましょう。