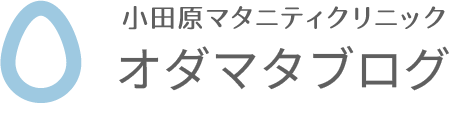不妊治療に取り組む中で、処方されることのある「プラノバール」という薬をご存じでしょうか。これは避妊薬として知られている一方で、実は不妊治療においてもさまざまな目的で使用される薬剤です。
「避妊薬がなぜ不妊治療に?」と疑問に思う方も多いかもしれませんが、プラノバールの持つホルモン作用が、排卵のタイミング調整や子宮内環境の調整に効果を発揮します。
今回は小田原マタニティクリニックより、プラノバールの役割をテーマにお届けしてきますので、ぜひご覧ください。
プラノバールとはどのような薬?
まずは、プラノバールとはどのような薬なのか見ていきましょう。
ホルモンバランスを調整する合剤
プラノバールは「卵胞ホルモン(エチニルエストラジオール)」と「黄体ホルモン(ノルゲストレル)」を組み合わせた合成ホルモン薬です。
もともとは経口避妊薬として開発されましたが、ホルモンを補う作用から月経周期の調整や排卵誘発後の黄体補充など、多様な医療目的で使用されています。
日本での処方状況
日本では医師の処方によって使用され、避妊以外の治療目的としては、生理不順、月経困難症、機能性出血、さらには不妊治療などにも用いられています。
不妊治療におけるプラノバールの使い方
続いて、不妊治療におけるプラノバールの使い方を見ていきましょう。
月経周期のコントロール
不妊治療では、採卵や胚移植のタイミングを計画的に行う必要があります。そのため、プラノバールを用いて人工的に月経を遅らせたり、周期を一定に整えたりすることがあります。
黄体機能低下の補助
排卵誘発剤で複数の卵胞を育てた後は、体内のホルモンバランスが一時的に乱れることがあります。このとき、黄体ホルモンが不足し、子宮内膜の維持が不十分になることがあるため、プラノバールで補充することで着床しやすい環境を整えるのが目的です。
プラノバール服用時の副作用と注意点
続いて、プラノバール服用時の副作用と注意点について見ていきましょう。
吐き気・頭痛・むくみなどの初期反応
ホルモン製剤であるプラノバールには、吐き気、頭痛、むくみ、乳房の張りなどが副作用として現れることがあります。服用を始めて数日で軽快する場合もありますが、症状が続く場合は医師に相談が必要です。
血栓症リスクに注意
長期間の連続服用や、高齢・喫煙習慣・肥満などのリスク因子がある場合、まれに血栓症を発症するリスクが指摘されています。
自己判断での中断はNG
治療スケジュールに基づいて使用する薬であるため、自己判断で服用を中止したり、タイミングをずらしたりすると排卵のズレや内膜の異常につながる可能性があります。医師の指示に従って正確に服用することが大前提です。
プラノバールを使うことへの不安について
不妊治療中の方にとって、「妊娠したいのに避妊薬を飲む」という構図に戸惑いを覚える方もいます。しかし医療現場では、プラノバールを「ホルモン調整剤」として利用する場面が多く、あくまでも着床率の向上や治療スケジュールの最適化が目的です。このような点を理解することで、不安や誤解を減らすことができるでしょう。
まとめ:不妊治療における「プラノバール」の役割とは?
いかがでしたか?今回の内容としては、
- プラノバールはエストロゲンとプロゲステロンを含むホルモン製剤で、もともとは避妊目的の使用が多かった。
- 不妊治療では月経周期の調整やホルモン補充などに活用される
- 副作用として吐き気や頭痛、血栓リスクがあり注意が必要
- 自己判断での中断はせず、必ず医師の指示に従う
以上の点が重要なポイントでした。プラノバールは正しく使えば、不妊治療の成功率を高めるための大きなサポートになります。正しい知識と医師との信頼関係をもとに、不安なく治療に臨みましょう。