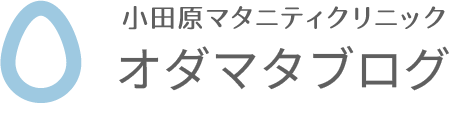不妊は誰にでも起こり得る問題であり、日本ではカップルの約6組に1組が不妊に悩んでいると報告されています。多くの人が「不妊=治療」と考えがちですが、実際には生活習慣の改善や病気の予防によって妊娠力を保ち、不妊症予防につなげることが可能です。
今回は小田原マタニティクリニックより、不妊症予防とさまざまな不妊治療の選択肢をテーマにお届けしていきますのでぜひご覧ください。
不妊とは何か
世界保健機関(WHO)は、不妊を「避妊をせずに1年以上性生活を行っても妊娠に至らない状態」と定義しています。不妊は女性だけでなく男性にも原因があるため、カップル双方が理解し、予防に取り組むことが大切です。
不妊の主な原因
続いて、不妊の主な原因について見ていきましょう。
加齢による影響
女性の卵子は年齢とともに数と質が低下します。
- 20代後半〜30代前半:妊娠率が高い
- 35歳以降:妊娠率が下がり、流産率が上昇
- 40歳以降:自然妊娠率は大幅に低下
男性も加齢とともに精子の質が低下し、DNA損傷率が上昇することが知られています。
生活習慣による影響
悪い生活習慣は妊娠に影響を与えます。
- 喫煙:卵巣機能を低下させ、精子数を減少させる
- 飲酒:ホルモンバランスの乱れを引き起こす
- 肥満・痩せすぎ:排卵障害や精子形成障害につながる
- 睡眠不足・ストレス:ホルモン分泌に悪影響
性感染症
クラミジアや淋菌は、卵管炎や精巣上体炎を引き起こし、不妊の大きな原因になります。特にクラミジアは女性不妊の重要な要因で、感染者の多くは無症状といわれています。
婦人科・泌尿器科疾患
子宮内膜症や子宮筋腫は、着床障害や卵管の癒着を起こします。また、男性の精索静脈瘤は、精子の質を低下させます。
不妊予防のためにできること
続いて、不妊予防のためにできることについて見ていきましょう。
生活習慣の改善
まず大切なのは生活習慣を整えることです。喫煙は卵巣機能を大幅に低下させ、実際に「卵巣を10年早く老化させる」といわれています。アルコールも適量であれば問題ありませんが、過度な飲酒はホルモンバランスを乱す要因になります。
また、体重管理も重要で、BMIが18.5〜25の範囲に収まっていることが理想的です。さらに、食生活では葉酸、亜鉛、ビタミンDといった栄養素が妊娠のしやすさに関わっていることがわかっています。
規則正しい睡眠
睡眠も妊娠力に直結する要素です。慢性的な睡眠不足は女性の排卵リズムを乱し、男性ではテストステロンの分泌低下を招きます。質の良い睡眠を心がけ、1日7時間前後を目安に休むことが推奨されます。
感染症予防
性感染症は不妊の大きなリスク要因です。感染を防ぐためには、性行為の際にコンドームを正しく使用することが基本です。さらに、無症状でも進行するクラミジアなどを防ぐため、定期的に性感染症の検査を受けて早期に異常を発見することが大切です。万が一感染が見つかった場合は、自分だけでなくパートナーも同時に治療を受けることで再感染を防ぐことができます。
定期健診の活用
不妊を予防するうえで、定期的に医療機関で健診を受けることも非常に有効です。婦人科健診では子宮や卵巣の異常を早期に発見できますし、男性も精液検査を受けることで精子の状態を知ることができます。特に婦人科疾患や性感染症は、早期に治療を始めるほど将来の妊娠力を守りやすくなるため、定期健診は積極的に活用するべきです。
不妊治療にはさまざまな選択肢が存在
不妊治療と聞くと、体外受精や顕微授精といった高度な方法を思い浮かべる人が多いかもしれません。しかし実際には、症状や原因、年齢などによって治療の段階はさまざまで、選択肢も幅広く存在します。もっとも基本的なのは「タイミング法」で、基礎体温や排卵検査薬、超音波検査を使って排卵日を特定し、その時期に合わせて性交を行う方法です。
排卵に問題がある場合には、内服薬や注射で卵胞の成長を促す排卵誘発剤を使うこともあります。さらに、精子を子宮内に直接注入する人工授精は、精子の状態や性交障害がある場合に有効で、比較的負担が少ない治療法とされています。
一方で、卵管が閉塞している場合や重度の精子異常がある場合には、卵管形成をして人工授精で自然妊娠を目指すか、卵子と精子を体外で受精させて子宮に戻す体外受精が検討されます。精子の数が極端に少ない場合には、顕微鏡下で卵子に精子を注入する顕微授精が有効です。
このように、不妊治療にはさまざまな方法があり、状況に応じた選択が可能です。
まとめ:不妊症予防とさまざまな不妊治療の選択肢について
いかがでしたか?今回の内容としては、
- 不妊はカップルの約6組に1組が経験する身近な問題
- 原因は生活習慣・感染症・疾患など多岐にわたる
- 生活習慣の改善が予防に有効
- 定期健診や性感染症検査で早期発見が可能
以上の点が重要なポイントでした。不妊は「治療」だけでなく「予防」できる部分が多くあります。生活習慣を整え、体の変化を早めにチェックすることが未来の妊娠につながります。夫婦で協力して早期に取り組むことこそが、一番の予防策といえるでしょう。不妊の予防策のひとつとして当院ではお相手を決めていない方に結婚相談所の紹介も行っています。