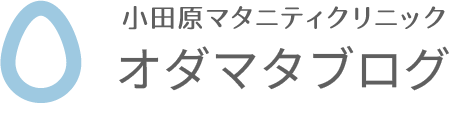出産を終えたあと、「頭がズキズキする」「重だるい感じが続く」といった頭痛に悩まされる方は少なくありません。
実は、産後の頭痛は ホルモンバランスの変化、睡眠不足、疲労、ストレスなど、複数の要因が重なって起こることが多いのです。
まずは、どのような原因が考えられるのか、そして頭痛にはどのような種類があるのかを見ていきましょう。
産後の頭痛の主な原因
出産後、妊娠中に増加していた 女性ホルモン(エストロゲンやプロゲステロン) が急激に減少します。このホルモンバランスの大きな変動が、頭痛を引き起こす主要な原因のひとつと考えられています。
さらに、授乳や夜泣きによる睡眠不足、慣れない育児によるストレスや疲労、抱っこや授乳姿勢による首・肩のこりなども、頭痛を悪化させる要因になります。
頭痛の種類
産後に多く見られるのは、以下の2つです。
①緊張型頭痛
長時間同じ姿勢を続けたり、肩や首まわりの筋肉がこわばることで起こる頭痛。
「頭をギュッと締め付けられるような痛み」が特徴です。
②片頭痛(偏頭痛)
ホルモンの変化や血流の乱れで起こる頭痛。
「ズキズキと拍動するような痛み」や「光や音に敏感になる」のが特徴です。
授乳中の薬の服用について
授乳中でも使用できる鎮痛薬はありますが、自己判断での服用は避け、必ずかかりつけの医師や薬剤師に相談したうえで服用しましょう。
また、薬によって一時的に痛みが落ち着くことはありますが、体のゆがみや筋肉の緊張など、根本的な原因が残っている場合は再発を繰り返すことがあります。
実は「骨盤のゆがみ」が関係していることも
出産によって骨盤は大きく開き、その後ゆっくりと元に戻っていきます。
しかし、回復の途中で骨盤がゆがんだままになってしまうと、背骨の位置がずれ、首や肩の筋肉に余分な負担がかかるようになります。
この筋肉の緊張が、緊張型頭痛などの原因になることがあるのです。
骨盤矯正で体を整えるメリット
骨盤矯正で骨盤や背骨の位置を正しい状態に戻してあげることで、体全体のバランスが整い、血流やリンパの流れが改善します。
その結果、首や肩のこりが軽くなり、頭痛が起きにくい体へと導くことができます。
また、骨盤まわりの筋肉がしっかり働くようになることで、腰痛や恥骨痛、尿もれといった産後特有のトラブルの予防にもつながります。
薬に頼る前に、体のバランスから整えるという選択も検討してみましょう。
まとめ
いかがでしたか。
産後の頭痛は、ホルモン・睡眠・姿勢など、さまざまな要因が重なって起こります。
痛みを我慢したり、薬だけでしのいだりするのではなく、根本的に「体のゆがみ」を整えることが大切です。